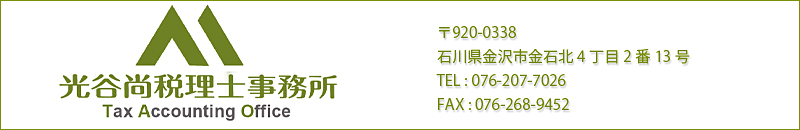お知らせ
10.92020
「2020年度年末調整は大きく変わっています」
2020年度は所得税の制度に大きな変更があることを前にお知らせいたしました。
当然給与の所得税の精算手段である「年末調整」も大きく変更となっています。
2つに分けて説明します。
まずは制度面(法律)です。
大きく次の3つです。
- 給与所得控除
- 基礎控除・所得金額調整控除額
- ひとり親控除・寡婦控除
このうち①は、給与所得控除が特に高額所得者において減額されました。最低65万円(給与収入65万円までは所得はゼロ)だった給与所得控除が55万円となりました。
また最高額が220万円から195万円となり、かつ適用される給与収入水準も下がっていますから、高額給与収入者は大幅な増税、そうでなくても全員が昨年度同じ「給与収入」でも「給与所得」は増加しています。
次に②ですが、①の給与所得控除額が65万円から55万円に10万円減少したことに伴い、基礎控除額を38万円から10万円引き上げて48万円としました。
これにより一定額以下の給与収入者の税負担は前年と同一になるように配慮されています。
一方所得金額2400万円以上の高額所得者は「基礎控除」の金額を段階的に減額し2500万円以上はゼロとするこにしました。
高額所得者は①でも増税になっているところに加えて②でも増税となるダブルパンチです。
しかしそれでは余りにも負担が大きすぎるということで、①②で税負担が増える、給与収入850万円以上の人について
「本人が特別障害者」「扶養親族等(控除対象配偶者を含む)が特別障害者」「扶養親族等が23歳未満」のいずれかの要件を満たせば、850万円を超える給与収入について10%(最高15万円)を別途控除する「所得金額調整控除」が設けられました。
これにより申告書の様式が大きく変わり、昨年までの「配偶者控除申告書」の用紙に、「基礎控除申告書」(高額所得者改正)と「所得金額調整控除申告書」を1枚に詰め込んだ「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書」というなんとも長い名前の申告書に改変されました。
そして従来、配偶者のいない給与所得者は「配偶者控除申告書」を提出していませんでしたが、今後は3つの申告書がセットになったこの申告者は「扶養控除等の申告書」同様全員が提出することになります。
最後に③ですが、従前問題になっていたのは
1 「寡婦控除」(女性)と「寡夫控除」(男性)の男女で大きな制度面の差があること
2 いわゆる「未婚の母」にこの制度の適用がないこと(一度結婚して離婚した「シングルマザー」には同制度の適用があるのとの差)
でした。
今回これを大幅に改善しました。
まず女性だけに認められていた「特別の」寡婦制度がなくなりました。
また基本的に「寡婦(夫)」という言葉を廃止し、すべて「ひとり親控除」という名前に統一しました。
この統一によって扶養する子がいるひとり親は、男だろうが女だろうが、結婚歴があろうが未婚だろうが全て同一の適用要件、同一の控除額となりました。
ただし従前の「寡婦控除」(女性)のうち扶養する子供がいなくても受けられる次の2ケース
1 離婚した女性で所得金額が500万円以下かつ扶養親族(子供でなくても可)あり
2 死別した女性で所得金額が500万円以下
の2つのケースは引き続き「寡婦控除」として残されました。
ということで完全には男女平等にはなっておりません。
次に事務的な面です。
ペーパーレスを背景にした「電子化年末調整」の採用を認めており、今までのように
例えば「保険料控除のはがき」を入手し、紙に明細を書いてはがきを添付して事業主に提出
といったことを、
従業員→事業主がパソコン上のやり取りで、さらには控除証明書も保険会社から入手した電子化した控除証明をつける、
といったやり方に変更することが可能となりました。そのためのソフトも国税庁HPで無償提供しています。
ただそのためには、従業員各自が事業主とオンラインされているパソコンを用意する必要があり、今のところ中小企業ではやや導入は難しいと考えます。
以上大幅に変更になっている年末調整制度を簡単に説明しました。
「変更といっても大変なことではない」
と高を括っていますと、従業員に控除申告書を配る時に説明ができず大慌てすることも予想されます。
年末調整の事務方は従前に十分に準備をお願いします。
なおすでに国税庁HPで
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
年末調整の詳しい説明ページを設けておりますのでぜひご参考ください。
最近のお知らせ
-
2024/6/27
-
2023/11/10
-
2022/1/20
-
2021/6/21
-
2020/10/9
-
2020/4/30